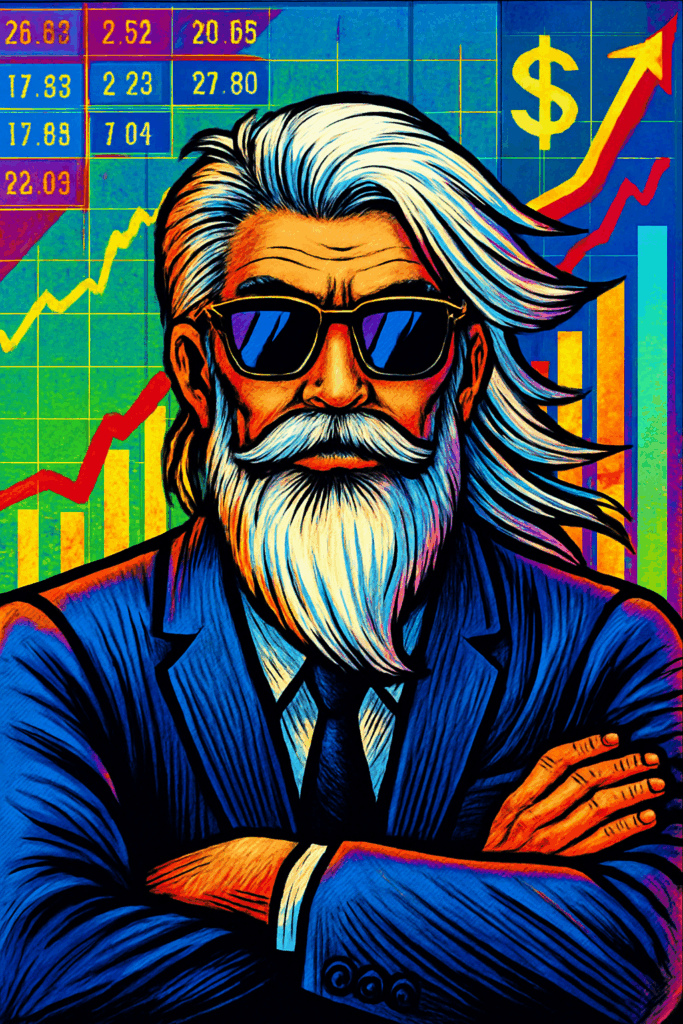「自分は売って助かった。あなたは…大丈夫?」という視線
その同僚は、最近株式投資を始めたばかり。ある日、こんなふうに話しかけてきました。
「なんか下がってきたから売っておいたんだよね。そしたらそのあともっと下がったから。。。」
そのときの同僚の表情は、どこか誇らしげでした。
そして私に対しては、「売らずに損を抱えてるなんて、かわいそうに…」というような目を向けてきたのです。
私は笑って流しましたが、心の中ではこう思っていました。
「いや、そういう見方もあるけど、私は長期で持つことで得られるリターンを信じている。
今売ることが、必ずしも“正解”とは限らないんだ。」
株価は下がっている。でも、企業の成績が悪いわけではない
2025年春の調整相場は、多くの投資家にとって判断の難しい局面となっています。

まず誤解のないように言うと、今回の下落は企業の業績が急激に悪化した結果ではありません。
Apple、Microsoft、NVIDIAなどの主要ハイテク企業は依然として好調な決算を発表しています。ではなぜ株価は下がっているのでしょうか?
主な理由は、以下のようなマクロ的な要因による“期待の調整”です:
- FRBの利下げが想定より遅れていることへの失望
- インフレ再加速への懸念
- ウクライナや中東情勢など地政学リスクの高まり
- 2023〜24年にかけての急騰(AI相場など)に対する過熱感の反動
つまり、「企業が悪いから下がっている」わけではなく、今は市場の期待が少し剥がれているだけなのです。
長期インデックス投資を続ける5つのメリット
1. 複利の力を最大限に活かせる
長期投資の真の武器は「複利」です。
利益を再投資することで、利益がさらに利益を生む“雪だるま効果”が起きます。
たとえば年利7%で運用すれば、10年後に資産は約2倍、30年後には約8倍になります。
この複利の効果は「時間を味方につけた人」だけが最大限に受けられるものです。
途中で売ってしまえば、その連鎖がリセットされてしまいます。
2. 下落局面は「未来のリターンの仕込み時」
積立投資は、毎月定額を買うため、価格が下がっている時には多くの口数を自動的に買うことができる設計です。
つまり、今のような下落局面は「将来の利益の種をまく時期」でもあります。
安く仕込んで、高く育てる──このスタイルが、インデックス投資の本質です。
3. 株式市場は長期で見れば成長している
過去100年以上、米国株式市場は多くの危機(リーマンショック・コロナショックなど)を乗り越え、結果的に高値を更新し続けてきました。
その都度、「もう終わりだ」と言われながらも、数年後には回復しています。
今回の調整も、未来から見ればただの通過点となる可能性が高いと私は思っています。
4. タイミング投資は難易度が高すぎる
一度うまく売れても、「次に買い戻すタイミング」まで完璧に判断できる人はほとんどいません。
短期的に見ればうまくいったように見えても、長期のトータルリターンで見ると「持ち続けていた方がよかった」というケースが非常に多いのです。
私は、自分が完璧なタイミングを見抜けるタイプではないと分かっています。
だからこそ、「何もしないことこそが最適解」だと感じています。
5. 新NISAは「長期で使う人」が最も得をする制度
2024年から始まった新NISAは、長期・積立・非課税運用を推奨する制度設計になっています。
【新NISAの主な特徴】
- 売却した分の非課税枠は翌年以降に復活する
- 非課税保有期間は無期限
- 運用益はすべて非課税
- 生涯投資枠は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
ただし、新NISAの非課税枠は保有残高ベースで管理されており、
枠を使い切ってから売ってもその年の再投資には使えず、翌年以降に復活します。
また、利益が出る前に短期で売ってばかりいると、非課税の恩恵も小さいまま枠を消費してしまうことになります。
制度を活かすには、非課税のまま長く運用を続けることがカギなのです。
まとめ:うまくやるより、続ける力が強い
たしかに、同僚のようにうまくタイミングを合わせて売れたことが「成功体験」になることもあります。
でも、それが毎回できるとは限りません。
私は、自分が未来を当て続けられるとは思っていません。
だからこそ、未来を信じて続ける投資を選びます。
「かわいそう」と思われても構いません。
数年後、「あの時やめずに続けていてよかった」と思える自分であるために、今日も私は、いつも通り積み立てを続けていきます。
2025年という年も、きっと将来「続けてよかった」と思える一幕になる。私はそう信じています。