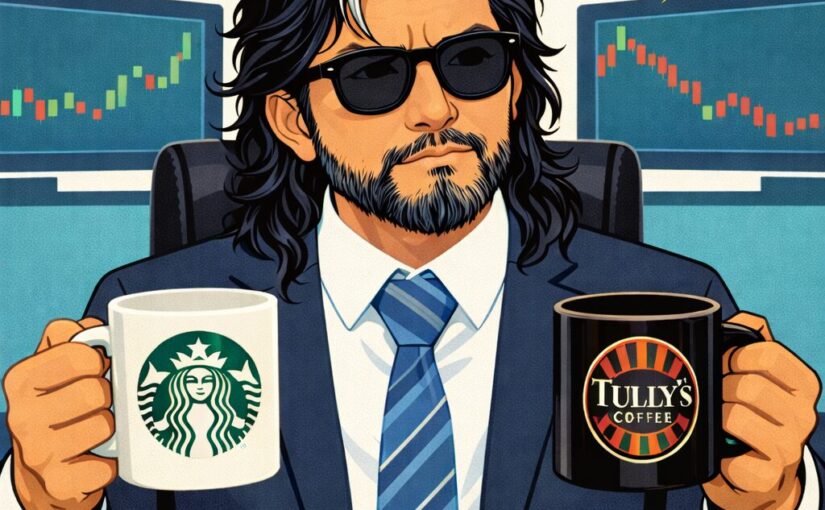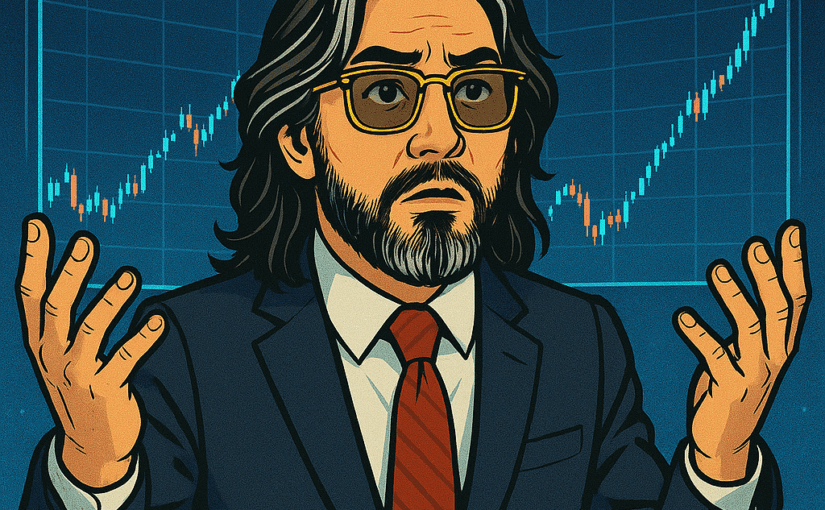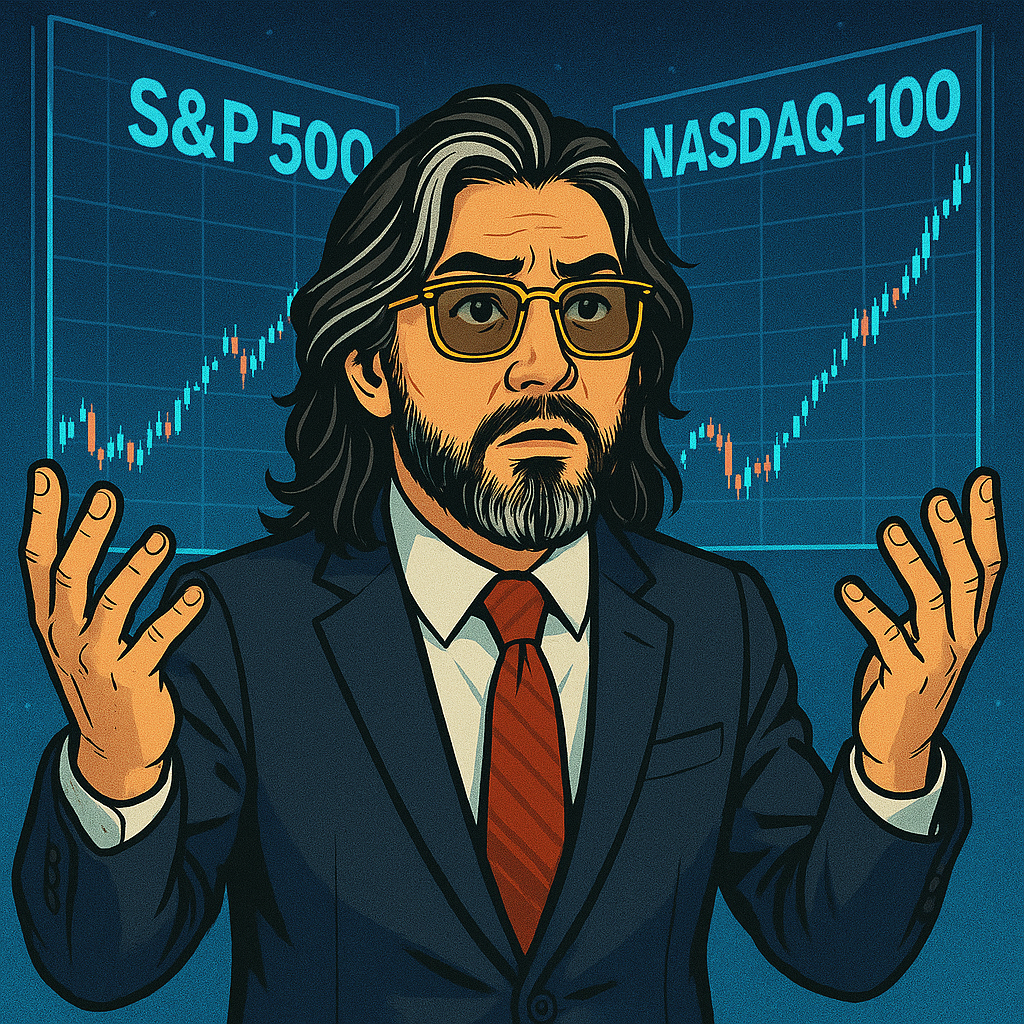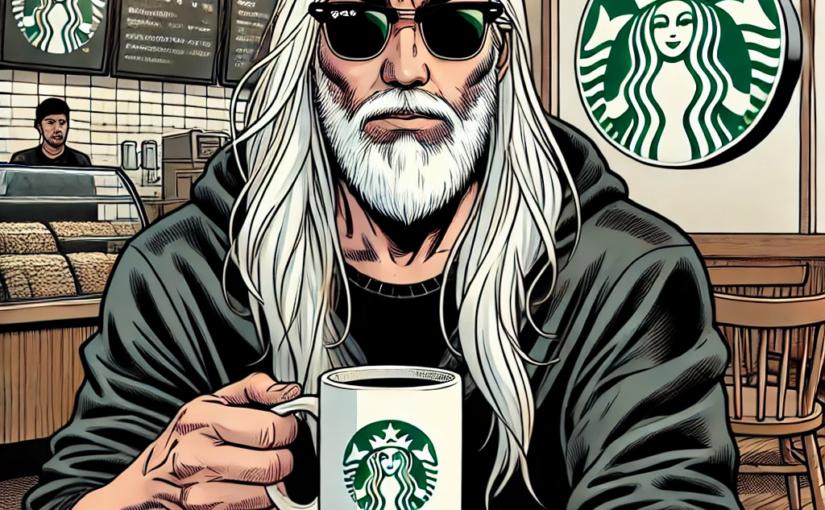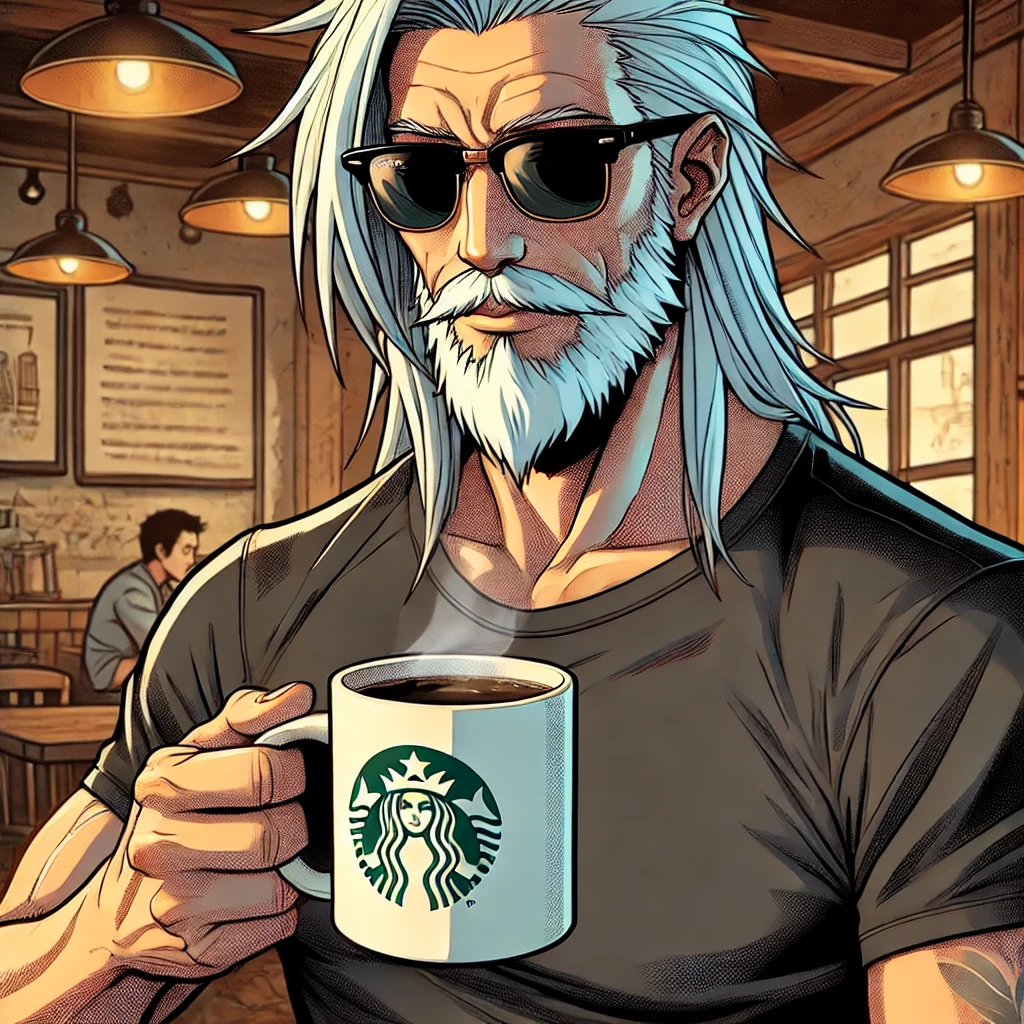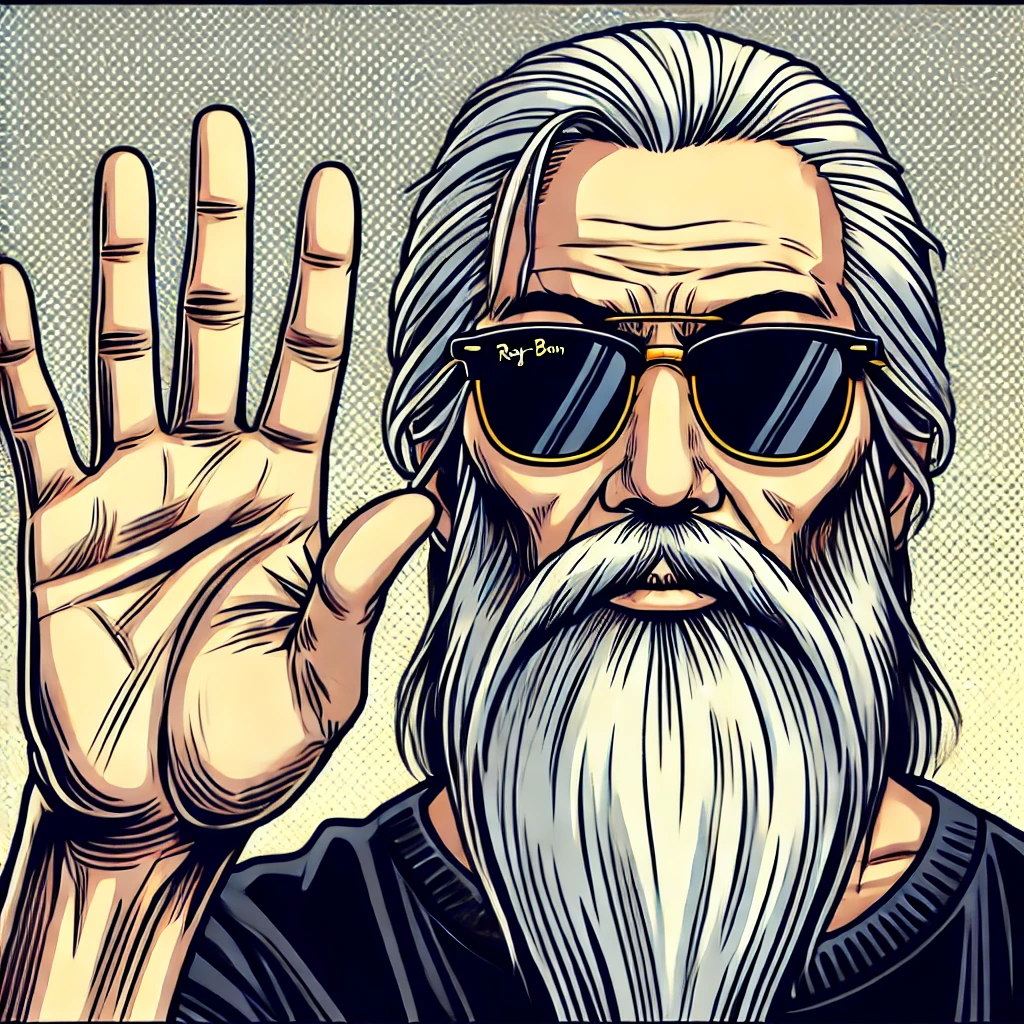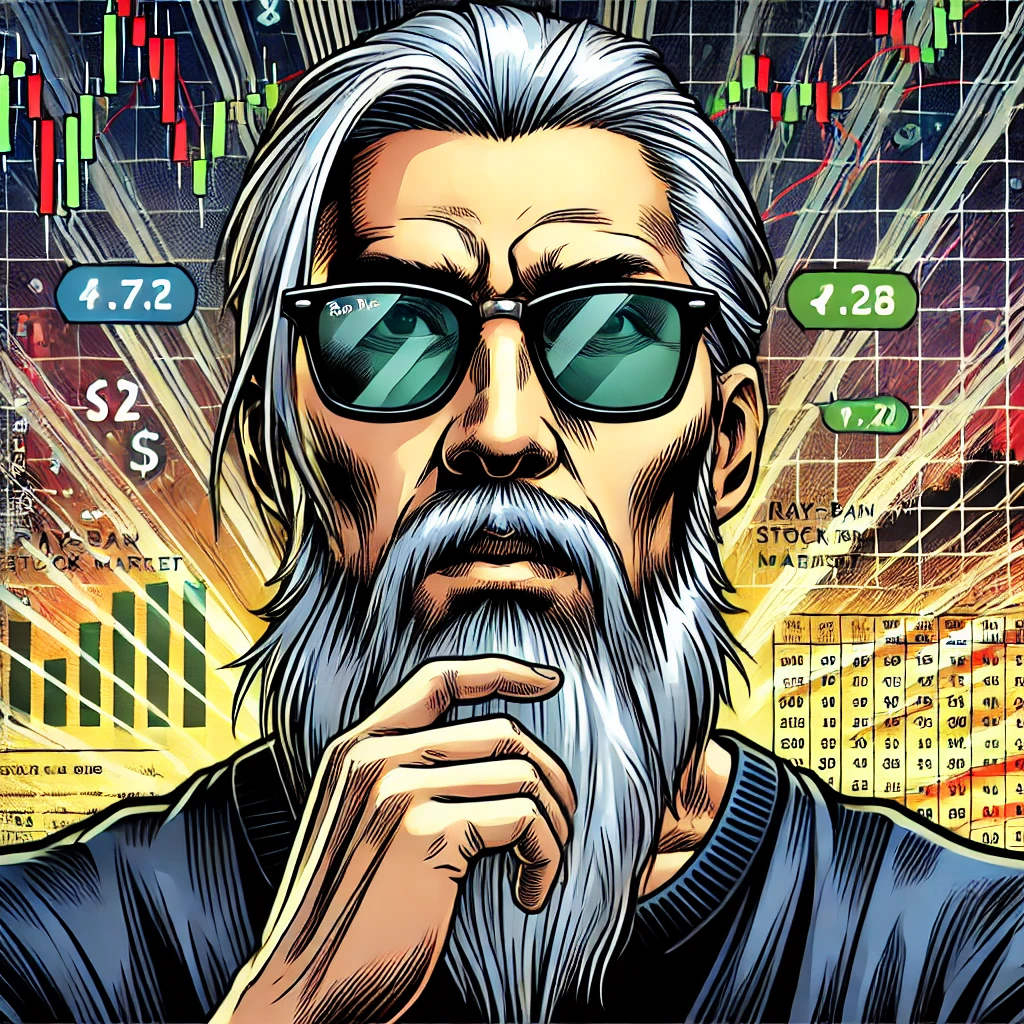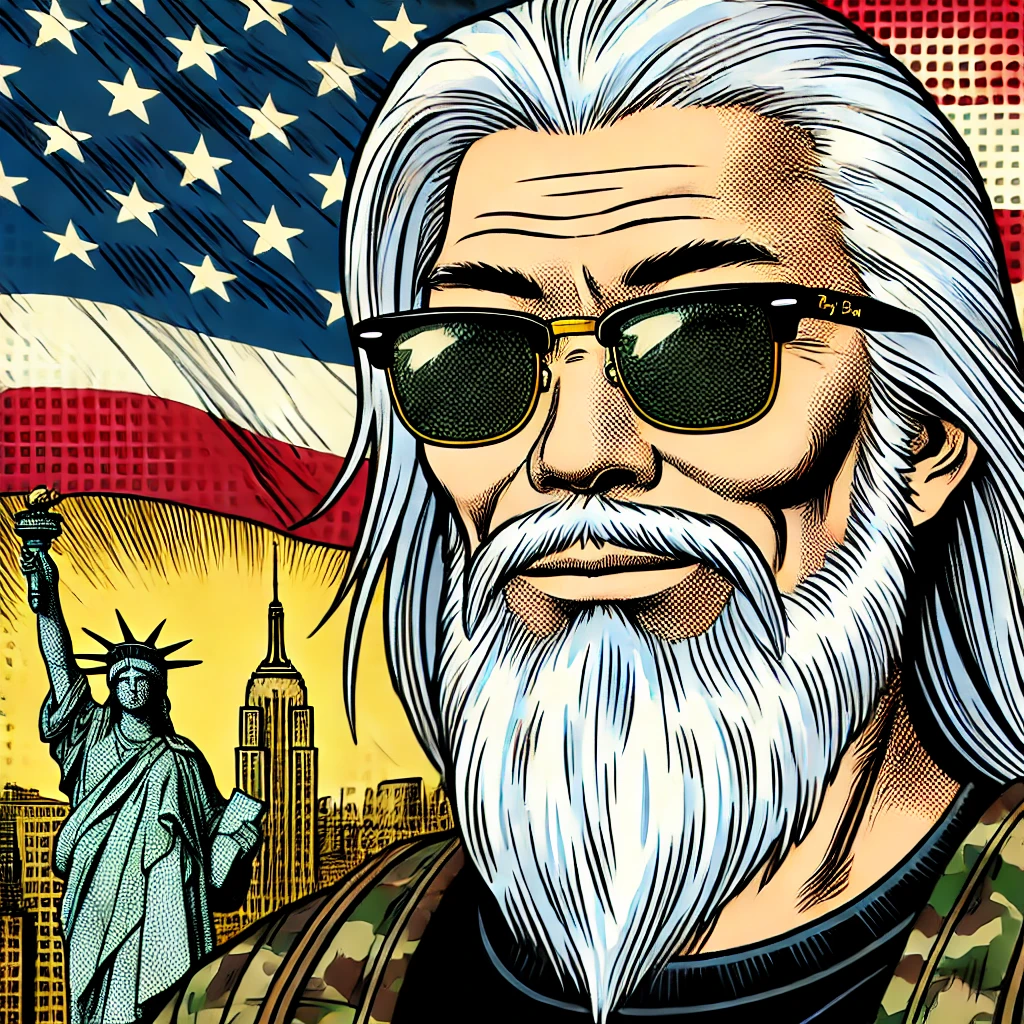この記事を読むと、
「何を買うべきか」「どこを応援すべきか」という問いから降りられる。
代わりに、
・なぜ長期インデックス投資家は揺れにくいのか
・なぜ暴落しても「裏切られた」と感じにくいのか
・日常の小さな選択に、どう意味を与えればいいのか
その思考の土台が手に入る。
これは、
相場を当てるための記事でも、
世界を変えるための記事でもない。
「個人では世界は動かせない」と分かった上で、
それでも自分の立ち位置を失わずに生きるための話だ。
長期で居座るための、
静かな足場が欲しい人に向けて書いている。
スタバか?伊藤園のタリーズか?
――長期インデックス投資家が「選択」と「帰属」に行き着くまで
AIは、これからだと思っている。
それは疑いようがない。
それなのに、株価はもうかなり上がっている。
「もう織り込んでいるのでは?」
「増えすぎでは?」
そんな素朴な疑問から、この思考は始まった。
資本主義は、なぜ右肩上がりなのか
考えてみると、AIは資本主義を押し上げるエンジンのほんの一部にすぎない。
人口。
生産性。
インフレ。
企業の淘汰。
制度。
AIは、その中の最新で目立つ歯車だ。
つまり、
資本主義が伸びるのはAIのおかげではない
AIがあるから、さらに加速しているだけだ
ここまでは、理解できている。
では、個人は何をすればいいのか?
そこで次の問いが生まれる。
AIを応援すればいいのか?
アメリカを応援すればいいのか?
スタバか?
それとも、伊藤園のタリーズか?
だが、すぐに現実にぶつかる。
私一人が何を選んでも、
経済に影響はない。
これは事実だ。
それは「選挙に行っても何も変わらない」と同じ構造
ここで、強い既視感がある。
選挙に行っても、1票で政権は変わらない。
だからといって、行かなくていい、とはならない。
消費も、投資も、同じ構造だ。
影響はない。
だが、意味はある。
この矛盾をどう説明すればいいのか。
ここで、「応援」という言葉が使えなくなった。
世界は「選択」で出来ている
少し視点を引き上げる。
この世の万物は、突き詰めれば選択の集合体だ。
どこで働くか。
何を学ぶか。
誰と付き合うか。
何を買うか。
どこに金を置くか。
すべては、大小の選択の積み重ねでできている。
選択一つ一つは、ほとんど無力だ。
だが、選択の方向性は、人生を確実に分ける。
だから私はずっと、
「選択は重要だ」と思ってきた。
選択は、結果を変えるためのものではない
ここで一つ、はっきりさせておく。
選択は、
世界を動かすためでも、
経済を動かすためでもない。
選択の本質は、ここだ。
自分がどの流れに身を置くかを決めること。
結果を操作するためではない。
立ち位置を固定するための行為だ。
応援ではなく、立ち位置の問題だった
世界を動かしたいわけではない。
経済に貢献したいわけでもない。
……いや、正直に言えば、
動かしたいし、貢献したい。
ただ、それが
個人ではびくともしない
ということも、分かっている。
動かしたいという意思と、
動かないという現実認識。
この2つは、矛盾しない。
影響ではなく、「帰属」を選ぶ
世界を変えられないからといって、
何もしないわけではない。
影響を与えられないからといって、
選択を放棄するわけでもない。
ここで必要だったのは、
影響力ではなく、帰属という考え方だった。
帰属とは何か
帰属とは、
自分の時間・金・注意力を
どのシステムに預けるかを決めること。
国家でも、企業でも、ブランドでもない。
システムへの帰属だ。
日本で暮らすこと。
米国指数に投資すること。
人は常に複数の帰属を持っている。
重要なのは、それを自覚して選んでいるかどうかだ。
長期インデックス投資家にとっての帰属
長期インデックス投資家にとっての帰属は、かなり具体的だ。
個別の勝ち負けや判断を放棄し、
文明レベルの成長に資産を委ねるという契約。
当てにいかない。
予測しない。
修正しない。
その代わりに、
判断しなくていい状態を、長期で買っている。
これが帰属だ。
なぜ、暴落しても動揺しないのか
帰属がないと、人はこう考える。
上がった。自分は正しい。
下がった。自分は間違った。
相場を、自分への評価として受け取ってしまう。
帰属があると、見え方が変わる。
私はこのシステムに属している。
システムには好不調がある。
今はそのフェーズだ。
ここには、自己否定も慢心も入り込まない。
帰属は「判断を外に出す」装置
帰属とは、
判断の責任を、
個人から構造へ移す行為だ。
個別株は自分の責任。
指数は構造の責任。
文明は歴史の責任。
スケールを上げるほど、心は安定する。
スタバか?伊藤園のタリーズか?
ここで、ようやく最初の問いに戻る。
スタバを選んでも、
伊藤園のタリーズを選んでも、
GDPも株価も変わらない。
それでも私はスタバを選ぶ。
理由は、経済効果ではない。
私はS&P500とNASDAQ100を保有している。
だから、同じ経済圏のプロダクトを使う。
これは信仰ではない。
自分の選択と帰属がズレていないかを確認する行為だ。
帰属がある人の強さ
帰属を選んだ人は、
上がっても驚かない。
下がっても慌てない。
それは冷静だからではない。
最初から、立ち位置が違うだけだ。
最後に
世界を動かしたいし、
経済にも貢献したい。
だが、個人ではびくともしない。
その現実も、はっきり分かっている。
だから私は、
世界を動かそうとしない。
経済を操作しようとしない。
その代わりに、
どの流れに身を置くかだけは、
自分で選び続ける。
だから今日も、淡々と積み立てる。
そして、スタバで朝食をとる。
スタバか?
伊藤園のタリーズか?
それは好みの話ではない。
帰属と選択の話だ。